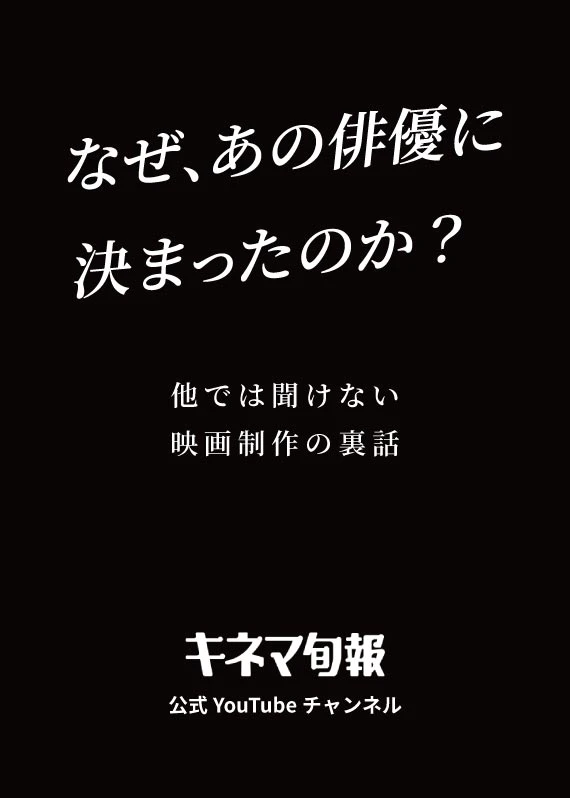ナチス台頭前夜の青年の物語「さよなら、ベルリン」、ドミニク・グラフ監督インタビューと本編映像公開
児童文学の大家エーリヒ・ケストナーの大人向け小説を映画化。ナチス台頭前夜の不安な時代を彷徨う青年を描き、ベルリン国際映画祭出品およびドイツ映画賞3部門受賞を果たした「さよなら、ベルリン またはファビアンの選択について」が、6月10日(金)よりBunkamuraル・シネマほかで全国順次公開される。ドミニク・グラフ監督インタビューと本編映像が到着した。





1931年、作家を志してベルリンにやってきた青年ファビアン。女優を夢見るコルネリアとの恋、ただ一人の「親友」ラブーデの破滅。ナチズムの足音が迫り、世界が大きく変わる予感の中で、ファビアンは「これからどこへ歩き出せばいいのか」と焦燥を募らせる──。
公開された映像は、ファビアンがコルネリアにドレスをプレゼントするシーン。恋に落ちて間もないふたりは瑞々しく、ベルリンで暮らすファビアンを心配して故郷からやってきた母親の姿も印象的だ。
ドミニク・グラフ監督のインタビューは以下の通り。
Q:この映画は、現代の地下鉄の駅から、1930年代初頭のワイマール共和国へと観客を連れて行く移動ショットから始まります。なぜこのようなオープニングにしたのですか?
現代とのつながりを作りたかったのです。僕はこの映画をドキュメンタリー風に始めたら素晴らしいだろうと考えました。僕たちはカメラを構えてトンネルを通り抜け、過去の時代に至ります。そこには光が降り注いでいますが、同時にドイツの最も暗い時代──これからどこまで暗くなっていくのかさえ分からないような時代でもあるのです。
Q:ケストナーの原作「ファビアン あるモラリストの物語」をどのように脚本にしていったのでしょうか?
僕がこの小説を初めて読んだのは、1979年の西ドイツでのことでした。魅力的な、素晴らしい文学だと思いました。何にもましてラブストーリーであり、対話であり、叙事的な観察記録であり……。僕は、“これはファビアンとコルネリアのラブストーリーにできる”と直感しました。街路やカフェを舞台にした、エピソードの集積からなるラブストーリー。そしてそれをめぐる時代性を、構造化を排した手法で捉えようと思ったのです。小説「ファビアン あるモラリストの物語」は、単なる状況や感情、考えの奔放な叙述として素晴らしい作例です。ある瞬間における、何人かの人物について記述したもの。その場面はほとんど全てケストナー的です。それはジャズのよう、終わることのない即興演奏のようだといえますね。
Q:トム・シリングを主役に据えようと思った理由はなんですか?
トム・シリングがこの役を演じたくないと言ったなら、僕はこの映画を撮らなかったでしょう。僕にとって彼は、この複雑な主人公を演じる上で理想的な俳優でした。
Q:この映画は部分的にスーパー8で撮られていますね。どのくらいデジタルで撮られているのですか?
80%くらいはデジタルで撮られていて、スーパー8の映像やベルリンを映したモノクロのアーカイブ映像を組み込みながら編集しました。とても音楽的な作業でした。
Q:ドイツでは近年、この時代を背景にした映画やテレビ作品が多く、それは「現代が当時の社会状況に似ているから」だという声を聞きましたが、どう感じますか?
はい、その通りです。危機的な政治状況のために、ドイツでは今再び、あの時代への関心が急激に高まっています。私は間違いなく2022年のドイツ社会を当時と重ね合わせています。あのポーランドや右翼・左翼の間で引き裂かれ、政治が麻痺した共和国と。しかし今、ドイツだけではなく、世界中のほとんど全ての場所が同じ状況にあると言えるのではないでしょうか?

▼場面写真クレジット
©Hanno Lentz/Lupa film
▼映画クレジット
© 2021 LUPA FILM / DCM Pictures / ZDF / Arte
配給:ムヴィオラ